�n�抮���^�̈�Â̐��i
�@���̓��{�̎Љ�͔̏��ɓ���Ȃ��Ă��܂��B�����m�̂悤�Ɂu�i���Љ�g�債�Ă���v�ƁA�����̂悤�ɐV�����ɂ��킵�Ă��܂��B��ÂƂ̊֘A�Ō����ƁA��̈Ӗ��Ŋi���Љ�̖�肪�\��Ă��Ă��܂��B�ЂƂ͂��������͂܂��܂��������ɂȂ�A�n�����l�͂܂��܂��n�����Ȃ�Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B�ł����ꂾ���ł͂Ȃ��āA��Â������Ă͂����ЂƂ̐V�����ۑ肪�o�Ă��Ă��܂��B���N�ȍ����ƁA�a�C�̍����Ƃ̊i���ł��B�n���Â̊ϓ_����A��Ԃɒ��ڂ���K�v������܂��B
�@�Ⴂ�l�͎��̂悤�Ɍ����܂��B�u�a�C�ɂȂ�̂́A�a�C�ɂȂ��������v�ƍl����l�����\�����Ă��Ă��܂��B�펯�ł͍l�����Ȃ��������ł����A�����̐����K�������ɃR���g���[�����邱�Ƃɂ���ĕa�C�ɂȂ�Ȃ��悤�ɓw�͂���Ƃ����ʂ͊m���ɂ���܂��B�u�a�C�ɂȂ�̂́A�a�C�ɂȂ��������v�Ƃ����������͏����������̂ł����A����̕��Ȃǂ͕a�C�ɂȂ�͖̂{�l�̐ӔC�ł͂Ȃ��̂�����A�Љ���ׂ��Ǝ��͍l���Ă��܂��B�������A���ꂾ���ł͋c�_���o���Ȃ����オ����Ă����̂ł��B���N�Ȑl�����ň�Â̂��߂ɂ��������Ƃ����C�����ɂ����邽�߂ɂ͂ǂ������炢�����B�V���ȉۑ肪�������Ă��Ă��܂��B
�@��Ë����̑̐��Ɋւ��ẮA�s���{���̖����͏d�v�ł������A��Ô�Ɋւ��ẮA�]���͍��̐ӔC�ƂȂ��Ă��܂����B�������A���܂͑傫���ς�낤�Ƃ��Ă��܂��B����݂Ȍ�����������̂ł����A�k�C���̕��ƒ���̕��������������N�ی��ɓ����Ă��ď�����������������A�ǂ��炪���������ی������Ă���Ǝv���܂����B�ӊO�Ȃ��ƂɁA���쌧�̕������������Ă���̂ł��B���ςł����A���ۂ������Ă����Ô�͖k�C���̕���1.5�{���炢�ł��B�]���̍��̍l�����́A�k�C���̐l�̕�����������a�C�ɂȂ�̂�����A����̐l�����������͕̂ς����ǁA����̐l���k�C���̐l���������ꏏ�������瓯�����������̂������̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂��]���̍l�����ł��B�������A�ǂ����Ėk�C�����������Ƃ����ƁA�~�ɂȂ�ƊF����������@�����̂ł��B�Ȃ����Ƃ����ƉƑ������b�����Ȃ�����B����͍K���s�K���Ƒ����ʓ|�����܂��̂ŁA�~�ɂȂ��Ă��ݓ����͐L�тȂ��̂ł��B�ǂ��������S������������Ǝv���܂����B�k�C���̕����撣���āA�H�v���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ƃ������܂��B�������A���쌧�ł́A����������������܂��B�u�m���Ɏ������͉Ƒ����ʓ|�����Ă���܂��B���̂��߂ɏ������ǂꂾ���]���ɂȂ��Ă��邩�B�v�Ƃ���������������܂��B��������ƁA���܂̖����ǂ������ӂ��ɕ��S���čs�����Ƃ������Ƃ��A���ՂȖ��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩��܂��B�����āA��Ô�Ɋւ��Ă��������n��ɐӔC�������Ă��炨���Ƃ������ꂪ�����Ȃ��Ă��Ă��܂��B�]�����t�����ŘA�g�ƌ����Ă����̂��A�}�����A���A�������A���ꂩ��ݑ�̂S���ږ�����Â̗������邽�߂ɁA�ǂ������d�g�݂ɂ��邩�Ƃ������Ƃ��A�o�ϓI�ȕ�V���܂߂āA���Ȃ苭������Ƃ������������ꂩ��i��ł����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�n���Ñ̐��̏[��
�@ ���ꂩ��̒n��̈�Ñ̐��̂�����́A10�N�O���猾���Ă���̂ł����A�I���ƏW���A���邢�͏W���ƑI���Ƃ��������������܂��B����ꂽ��Ô���ǂ̂悤�ɗL���ɔz�����邩���l���Ȃ�������Ȃ����オ����Ă��܂��B��������ς���Ə����������炨��҂���ɍs�����̂����܂œs�s���ł���������ǁA����͏����]���ɂ��āA2�a�@���������̂�1�ɂ��Ă��܂��A����1���[������A�����s�ւɂȂ鎖������Ȃ��Ɠ�����オ����Ă��܂��B�������������p����������i�����Ƃ��Ă��܂��B
�@����̃l�b�N�͉����ƌ����ƁA����҂��m�ۂł��Ȃ��Ƃ����b������܂��B�]�������t�͖��N1.6���̗��ő������Ă��܂��B�������A����҂̐L�т͖��N3�����炢�ŐL�тĂ��܂�����A�g�[�^���ł͂���҂���̋����͒ǂ����܂���B�a�C�̐��̑������ɔ�ׂĂǂ����邩�Ƃ����ƁA�I���ƏW�������Ȃ��Ƃ���҂���̋����A�m�ۂƂ����ϓ_����͓���ł��B�ǂ����Ă�����҂���́A��������̋@�\���W�����Ă���Ƃ���֍s��������X��������܂��B�����������Ƃ����܂��āA�ǂ����������邩�g�[�^���Œn��̈�Â����݂̐����𗎂Ƃ����ɋ@�\�����߂Ă����������ꂩ��̉ۑ�ƂȂ�܂��B
�@���J�Ȃ́A���A�]�����A�}���S�؍[�ǁA���A�a�A�����~�}���܂ޏ�����ÁA���Y����ÁA�ЊQ��ÁA�ւ��n��ÁA���ꂾ���ɏœ_�ĂāA���������n���Ìv��ŁA�ǂ������@�\���ǂ��ɂ��邩�����āA�����s�ւ����m��Ȃ����ǁA�ǂ��ɍs������ǂ�Ȉ�Â����邩�����悤�Ƃ���������ł��o���Ă��܂����B
��Ô�K�����̌���
�@���͍���A���ҕ��S��ʂɂ��Ăǂ����邩�Ƃ����O���t�������܂����B�i�}1�j
���ҕ��S��ʂɂ�28���~�ł��ƁA���Ɍ��������߂�����������܂��B�����Ȃ�o�ύ��������c�́A���҂��炨�������炤�̂͂����Ƒ��₵�āA�����f�Â��F�߂���ǂ��ł����Ƃ����c�_�����Ă���܂��B
�@���͌��I�ɕۏႷ���Ô�͂ǂ����Ƃ������ƂŁA���J�Ȃ����������Ă��o���܂����B���J�Ȃ̗\���́A28���~����40���~�ɂȂ�56���~�ɂȂ邪�A�s���N�̂Ƃ���܂ʼn����܂��Ƃ����������ł��B�O���t�������ɂȂ�Ƃ킩��܂����A�o�ύ��������c�͉��F�̂Ƃ���ɂ��ė~�����Ƃ��������������Ă��܂��B
�@���̉��F�͔N��ʁi5�����݁j��l�������Ô�A���ƑS�R�ω����Ȃ��Ƃ����ꍇ�ǂ��Ȃ邩�Ƃ��������Ƒ�̎��Ă��܂��B������i�ނ���A�ق��Ă����Ă����F���炢�͍s���܂��B���̉��F��42���~��56���~�͂��܂�ɂ��Ⴂ������̂ł��B����͌��J�Ȃ̐����̎d���̎��s�ŁA����Ȃɏオ������̂ł��B���̎��Z�͌i�C���ǂ��Ȃ�Ƃ��̂悤�ɂȂ�܂��B
�@�i�C���ǂ��Ȃ�Ƃ݂�Ȃ̋������オ��A����҂���̋������グ�Ȃ��Ƃ����܂���B���̏ꍇ�A56���~�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�ł��ʂɂǂ����Ă��Ƃ���܂���B���ۂɑ厖�Ȃ̂́A�������Č����Â炢�����m��܂��A�J�b�R�̒��̐������厖�Ȃ̂ł��B�݂�Ȃ̋������オ��ƁA����̍����������オ��܂��B�����Ĉ�Ô�����̎��͏オ��܂����A���͑���������A���邢�͑�GDP��ł��B���ݑ�GDP���5.4���ł��B���̂܂܂����ƍ���ɂ����5.7%�ɂȂ�5.8%�ɂȂ�܂��B���邢�͌��ݍ���������ł����ƁA7.3%�ł����A7.7%�ɂȂ�7.8%�ɂȂ�܂��B���ꂮ�炢�͏オ��̂͊ԈႢ����܂���B�m���ł��B
�@���ۂɑ厖�Ȃ̂́A�������Č����Â炢�����m��܂��A�J�b�R�̒��̐������厖�Ȃ̂ł��B7.3%��7.8%�ɑS�R�ǂ����Ă��ƂȂ��L���ȎЉ�̂��Ƃ��l����Ƃ��������Ȃ��z�Ȃ̂ł��B10.5%�ɂ����Ƃ��Ȃ肫���Ƃ������������܂����A����ȂɂȂ�Ȃ��Ǝ��͌����Ă���̂ł����A����ł͒ʗp���Ȃ��̂ŁA���J�Ȃ͐Ԃ��s���N�ɂ���Ƃ��������悤�Ƃ��Ă��܂��B
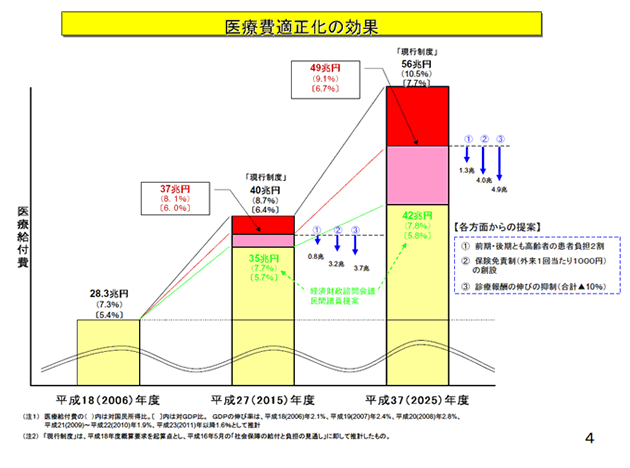
�@ ����̗\���̐ԂɂȂ�Ȃ����߂ɁA�����K���a�̗\�h�̓O��A���E����2025�N���炢�̎��ɂǂ����邩�Ƃ������Ƃ��l���ĉ������B
�@���۔�r�Ō����܂��ƁA���{�̈�Ô�͔��ɒႢ�ł��B�Ⴍ�ĕ��ώ����͐��E��ł��B���{�̈�Ô�ǂ����ď��Ȃ����ނ��A�܂����{�l�����O���A��i���ɔ�ׂĕa�C�ɂȂ闦�����̒Ⴂ�̂��́A�H�����ł��B���{�l�̎����������̂́A���Ȃ�̕����͐H�����ł����B���m�Ɍ�����0�Ύ����ϗ]���Ɋւ��Ă͐H���������ɏd�v�ŁA65�Ύ��_�̕��ώ����Ɋւ��Ă͈�Â����Ȃ�d�v�A�܂�Ō�̒i�K�Œ������������鉄�����ʁA��Â͂����Ƃ��𗧂��Ă���܂����A�Ⴂ������a�C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł́A�H���������ɏd�v�Ȗ������ʂ����܂��B���ꂪ�ЂƂB
�@���ꂩ��ӂ��ڂɁA���ύ݉@�����̒Z�k�A�ݑ��Â̑��i�A�a���]���ł��B��Ï]���҂̐l�B�͗×{�a�����Ȃ����Ƃ����̂��ƌ������Ƃ��Č����Ă��܂����A�ꌾ�ł����Ƃ��ꂩ��́A�����Ɍ��Ɩ����A�g���āA���ꂼ��̋}�����A���A�������A�ݑ��A�g���Ă������Ƃ������Ƃ���Ô�Ɋւ��Ă��d�v�ȉۑ�ƂȂ�܂��B
�����K���a��̌���ƍ���̕���
�@�����K���a�ƌ������Ô�{���ɑ����̃E�G�C�g���߂Ă��܂��B���́A�����I�Ȑ����K���a�̑��s���{���Ɉϑ����āA���͂ɂ�낤�Ƃ��Ă��܂��B���A�a�̈�Ô��1���~����܂��B����������ɃR���g���[���ł��邩�͂��ꂩ��̓��{�̏d�v�ȉۑ�ł��B��̓I�ɂǂ�����̂��Ƃ����ƁA�܂��P�N�����ď��������܂��B20�N�x���獑���^�����X�^�[�g���悤�Ƃ��Ă��܂��B
�܂Ƃ�
�@1�̓N���e�B�J���p�X�A���ɘA�g�N���e�B�J���p�X�A��Ë@�ւ��܂�����悤�ȃN���e�B�J���p�X�̊J�������ꂩ��̏d�v�ȃe�[�}�ƂȂ�܂��B������O�ł������Җ{�ʂł��B���҂����S�ł��B
�݉@�����̒Z�k�͏]�����猾���Ă��܂������A���������v���ɂ܂��܂����Ԃ�������܂��B
�@���ꂩ�獡��̃e�[�}�Œn��Ƃ����L�[���[�h�̏d�v�����܂��܂����܂��Ă܂���܂��B�����čŌ�ɓs���{���̖��������͑傫���������ƍl���Ă���܂��B
�@ �{�錧�̐��m�����s���{���̖��������߂邽�߂ɁA�u����҂�����R���g���[�����錠�����^�����Ȃ��̂ɂǂ����Ĉ�ÑS�̂��v��I�ɔz�u���邱�Ƃ��o����̂ł��傤���B�v����͑�ωs�����_�ł��B�s���{���P�ʂł����ȍs����i�߂悤�Ƃ��Ă���܂����A�����������قLj�t�̖�肪�o�Ă��܂��B���ۂɈ�ǐ��x���A���C�㐧�x�̓����ɂ���đ����ω��𐋂���Ƃ������܂����A����������t�̋����̂�����ɂ��āA�v�������{������Ȃ��ƁA���ܐ������������Ƃ��������Ȃ��Ƃ������Ƃ������܂��B�����A���J�Ȃ����_����̂Ō����Ă����܂����A�ւ��n���Ɋւ��Ă͗͂����Ă�낤�Ƃ��Ă��܂��B�������A��s�s�Ɋւ��Ă͂���҂���Ɋւ��Ă̋����̂�����A���Ƃ��A�a�@�̐������邩���m��܂���B���̎��ɓK�ɂ���҂����܂��Ĕz�u�����悤�Ȏd�g�݂��ǂ����邩�A�܂��܂����ꂩ��c�_�����Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��i�K�ł���Ƃ������Ƃ������܂��B�ǂ������������肪�Ƃ��������܂����B�i�u�����e�͕ҏW�̓s����ꕔ�ȗ������Ē����܂����j
���v���t�B�[�����i�h�̗��j
���� ���O ��
���s��w��w�@�o�ϊw������ ����
���̈�@�@��Ìo�ϊw�A�����o�ϊw
1972�N�@���s��w�o�ό���������
1975�N�@���l������w�o�ϊw��������
1981�N�@���s��w�o�ϊw��������
1987�N�@�� ����
1978�|1980�N�����1985�|1986�N
�@�@�@�@�@ �n�[�o�[�h��w���Ό������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
1990�N �@�� ��w�@�o�ϊw�����ȋ���
1999�N10���`2000�N3���@���@�����Ȓ�
2004�N4���@���@�����Ȓ�
<�w��ق�>
���{�o�ϐ���w����A���{�o�ϊw��A���{�����w��
���{�ی��w�����A���{�ی���Ís���Ȋw��]�c��
(��)��Ìo�ό����@�\���ψ�
�Տ��o�ϊw������iSociety for Clinical Economics�j����
�����J���ȎЉ�ۏ�R�c���Õی�������ʈψ�
<��v����>
�u�����Â̌o�ϊw�I���́v�i1977�A���a�J���t�����h�Ёj
�u�a�@���Љ�̌o�ϊw�v�i1982�A�o�g�o�������j
�u��Â̌o�ϕ��́v�i1987�A���m�o�ϐV��Ёj
�u���p�~�N���o�ϊw�v�i1989�A�L��t�j
�u��Âƕ����̌o�σV�X�e���v�i1997�A�}�����[�j
�u�ی��ƔN���̌o�ϊw�v�i2000�A���É���w�o�ʼn�j
�u������Љ�ƌ��������v�k���Ғ��l�i2003�A���É���w�o�ʼn�j
<��>
�h�������h���u�Տ��o�ϊw�v�i����j�i1991�A�����X�j
|