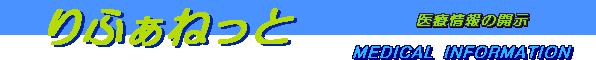 ● 患者が創る自分の「病歴カード」 ●
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 表−1 | ||
|
告知できなかった理由
|
||
|
90-98年
|
||
|
1
|
患者の「知りたくない」意志 |
0
|
|
2
|
超終末期(意識障害など) |
6
|
|
3
|
これまでの治療を尊重 |
4
|
|
4
|
家族の強い反対・懇願 |
9
|
|
5
|
主治医の熱意不足 |
7
|
|
6
|
説明を理解できない |
5
|
|
計 31名
|
||
予想されたように、家族の反対が根強い(9名)。 「主治医の熱意不足」(7名)というのは、私のチームの熱意がもう少し強ければ「告知」できたと推測されるケースである。在宅ホスピスケアの時間は、十分には長くない(私たちの91名の経験では、死亡までの期間は84日という短時間であった)。在宅での療養の最初の数日にその努力を最大限にしないと適当なタイミングを失ってしまうことも少なくないのである。「これまでの治療を尊重(4名)」というのは、専門医療機関で虚偽の説明を受け、それを否定するのもはばかられ、また、突発的な症状の急変で再入院する場合を想定すると、簡単には覆して、「実はこうでした」とは説明できないというものである。
いずれにしても、今後はますます患者自身の「意思表示」が重要となってくる領域である。
6.どのように役立つだろうか
この「病歴カード」の有用性は以下のようにまとめられる。
a.患者自身が自分の健康や病気について責任をもつ意識が芽生える。
・健康・病気の歴史を見直す。
・アレルギーなどの問題を整理できる。
・がん告知、延命治療の問題への手がかりとなる。
b.主治医が自己の責任を自覚し、患者との間に信頼関係が形成されやすい。
c.診察の場において有効である。
病気にかかった日時や、その他重要な項目は、平常時に文書化しておくことが大切である
d.ICカードによるものとちがって患者が自分で読み、訂正できる



(本文の無断掲載ならびに転写は、お差し控え下さいますよう、お願い申し上げます。)
[ HOME ]