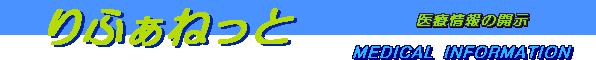 ● 「日本におけるマルプラクティス(医事紛争)の現状とその背景」 ●
医療事故調査会代表世話人
はじめに
平成7年4月22日、数回の準備会を経て、医療事故調査会がスタートしました。
江戸時代までの日本の医療史は、その診断治療が及ぼす効果が限定的なものであったということも含めて、社会的にもそれほど重要視される部分ではありませんでした。事実、医師になるより、儒学者になる方が魅力的だったという記述があります。
しかし、明治2年のドイツ医学導入の決定以来、明治政府は積極的に医学医療の整備に取り組みました。学問は東京帝国大学を初めとする帝国大学を中心として、各地域に広められ、医療は国公立病院、日本赤十字、済生会等の準公的病院を通じて提供されてきました。以来、日本の近代医療は常に国家から国民に与えられるという形式で進められてきました。このことが官尊民卑の意識の下に国民にとっては、受け身の姿勢を現在まで残すこととなったと思われます。学問を主体におく大学は、医局講座制という教授1人、助教授1人、講師2人、助手数名という閉鎖的チームによる個別システムの集合体として構成されてきました。各々の専門家がすべてこの形態で存在し、総体として大学医学部をかたちづくっているのです。このことは戦後、地方大学に医学部がつくられ、また私立医大、各県一医科大学構想で大学医学部が新設されていく中でも、基本的には全く変わりませんでした。
勿論、国立佐賀医大、筑波大、東京女子医大のように、臓器別等の新しい形態を採用するような大学も数少ないですが存在しています。しかし基本的には、この医局講座制が日本全国に最も広まっているといえます。学問を行う為に当初は、機能的にも有効であったと思われるシステムですが、分化及び深化が進み、かつ相互関連性が必須となった現在では、学問体系に合わない、また臨床医学という観点からは、その進展を妨げるような機能をもつ欠陥が明らかとなりました。昭和40年の前半に、その結論に基づいて大学医学部闘争が巻き起こったのは記憶に残っていると思います。医療は地域においても官公立を主体にした上意下達方式で与えられてきたため、需要者である住民にとって適切な医療への関わり方が行いにくいシステムが残っていました。それは、自由標傍制による診療科の不明瞭な実態、専門制の優位による適切な医療の選択の困難さ、診療時間の制限、救急医療の遅れ、あるいは精神科医療における隔離方式等に代表されるものです。
一方、医師を中心とした教育学問体系が優先された為に、医師以外のコーワーカーは学問的にも医師に従属するような型がとられ、看護婦教育は最近になって大学教育カリキュラムが採用されましたが、まだ専門学校カリキュラムと併存しています。同じことが、検査技師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語療法士等にみられます。唯一、言語療法士は、主として大学教育カリキュラムをマスターした人達によって担われています。また、メディカルソーシャルワーカーという本来医療の場には不可欠な職種も、やはり大学教育カリキュラムを経た人間が担っていますが、残念なことに今は国家資格がなく、放置されています。このような医師中心型の人間構成が、現実の医療の場では色々な弊害を起こす原因となってきたわけです。
昭和32年に国民健康保険法が施行されて、国民皆保険制度が確立しました。この保険制度は、いつでも、どこでも、誰でもが同じような医療を希望に応じて受けられるという基本性格をもっていますが、保険そのものの具体的な内容は物中心であって、決して知的評価を中心に据えたものではなかったのです。健康保険法の基本をつくるときに、医師が自らの知的評価を放棄し、当然のこととしてコーワーカーの知的労働評価も含めて点数配分等を官僚の手に委ねた為に、実にそれ以降現在まで差益依存型経営が維持され、そのことが医療事故にも結び付く原因になっています。このような背景の中で培われた現状は、住民の側からみれば、『お任せ型』でかつ『おしん型忍耐』を要する保険.医療.福祉であったわけです。例えば、病院という施設に一歩足を踏みいれたときから得られる不平等感、もともと疾病を持つという苦痛があるにも関わらず、なおかつ施設からもあるいは人からも受ける不快感に耐えるという時代がつい最近までみられました。昭和60年の第1次医療法改正に始まる平成医療改革は、官制のものではありますが、このような不備な点を積極的に是正することにより、新しい時代にみあったシステム作りを目指しています。
今、一番必要なことは、住民の側からこの医療改革への積極的な参加でしょう。そのことがシステムの変化に生命を与えることとなり、お互いがより緻密な医療を協力してつくり上げることができます。その過程で、医療事故の減少、及び多様な予防等の実施ということも可能となるでしょう。 |
 

[ HOME ] |