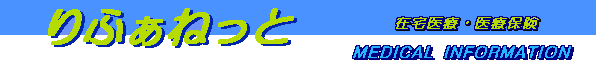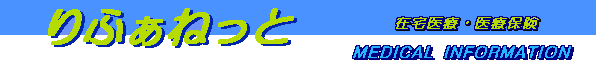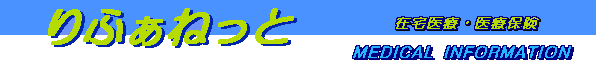
● 在宅高齢者ケアにおける摂食・嚥下障害
●
地域ケアおける口腔ケアの目的
提供: 大阪府作業療法士会学術局研修会
講演2 社団法人守口歯科医師会 副会長
吉田歯科医院 吉田春陽
●はじめに
(介護保険法第1条の規定)
この法律ほ、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他医療を要する者等について、これらの者がその育する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係わる給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
*"入浴・排泄・食事の援助"が在宅ケアの柱
●訪間口腔ケアの目的
1)食生活の維持改善
(1)座位の確立=寝たきりを脱するためのリハビリテーションケアの出発点
・嚥下性肺炎の防止
・ファウラー位、セミファウラー位時の注意点→後頚部筋群の拘縮(=気道伸展位)
・褥瘡予防対策としての坐位(日本医科大学 竹内孝仁教授)
(2)拘縮の予防改善=食生活の自立を目指す
・用不用の原則=残存機能の維持改善(=利き手変換)
・ブラッシングはかなり巧緻性が要求される生活動作
(3)生活(サーカディアン)リズムの形成=ノーマライゼーションの実現
・歯科的な意味でのノーマライゼーション?
『決まった時間に、家族と一緒に、同じ食卓で、食事を摂れる』こと
・寝て、起きて、食べて、排泄してを同じぺッドの上で済ますのほ"生活者" の姿ではない。
(4)咀爵嚥下機能の改善=リハビリテーション歯科医療
・経口摂取へのチャレンジ:栄養土とのタイアップ→咀爵嚥下訓練食の開発
・嚥下障害、言語障害のアセスメント・トゥールの開発(大阪府のアセスメント票)
・専門職による摂食嚥下機能訓練=在宅ケアスタッフとしてSTの配備の必要性
(5)栄言管理
・調理指導=寝たきり老人の発生を予防
・長寿化の要因:医学医療技術の進歩
・食生活の改善・住環境の改善
基礎体力、予備力の改善→感染症に対す抵抗力の増強
・脳卒中,骨粗鬆症は食生活の改善で予防可能→介護者家族に対する"草の根健康教育"
・食事内容の改善→QOLの向上
・栄養士の配備または協力体制
・水分摂取量の管理:高齢者は脱水症予備軍
(6)排泄の管理
・出入りのバランスの把握=食べられない原因は何か
・食べられない原因としての排泄恐怖症や介護者に対する遠慮など=
プライドに関わる問題障害歴の浅い人ほどこの傾向ほ強い
|