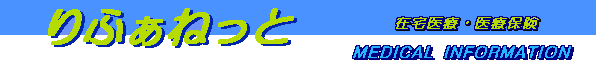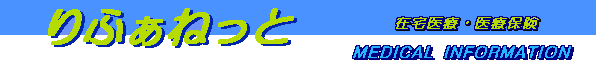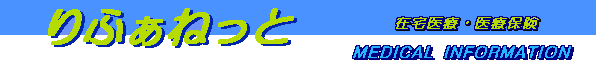
● 在宅高齢者ケアにおける摂食・嚥下障害
●
地域ケアおける口腔ケアの目的
2)コミュニケーション手段としての言語と表情の確保
(1)舌、口輪筋、表情筋などの運動機能訓練=表現手段の確保
・用不用の原則
(2)会話の確保=発音
・構音機能の維持改善
・在宅ケアスタッフやボランティアの役割
(3)社会性の確保=閉じこもり症候群(寝たきり予備軍)の発生防止
・寝たきり、痴呆は閉じこもりがつくる(日本医科大学 竹内孝仁教授)
・孤独というニードの発見の大切さ
・通所ケアの活用
*"家族・ポランティアの役割"を視野に入れたケアプランの構築
3)口腔内の保清
(1)口腔衛生指導(プラークコントロ―ル)
・要介護者や重症患者にとって口腔ケアは生命に関わる問題
高齢死亡者の70%以上に無症候性の肺炎が認められる(剖検)
口腔ケアを徹底することで有意の差をもって嚥下性肺炎の発症を抑制できる
"嚥下性肺炎の予防" (消化器外科病棟での歯科の活躍)
病棟に"口腔衛生管理者"を置けば医療費削減につながる
・経管栄養(経鼻腔、胃瘻、中心静脈栄養等)の患者の口腔ケア
"使わない口が最も汚い"
・本人にはリハビリテーション効果を期待
ブラッシングは "巧緻性が要求される生活動作"
・保清目的のプラッシングは介護者に期待→介護者の理解と協力
・マヒ側には食物残渣が停滞し易い→腐敗物嚥下による下痢
・食物残渣やプラークによる口臭と排泄物が寝たきり者特有の異臭→社会的孤立の解消
病院・施設では"口臭の育無"で施設ケアのレベルが分かる
・食事前の口腔マッサージやブラッシングは食事の導入を促す
(2)ウ蝕、歯周病の進行抑制=狭義の歯科口腔衛生指導
・寝たきり高齢者の口腔環境の特性→ph.が酸性傾向を示すことが多い→根面ウ蝕の発生
・在宅訪問歯科治療の限界=歯牙切削や外科処置は原則として行わない→施設での診療
(3)味覚の確保=味覚は中枢への大きな刺激
・清潔な口腔環境は食事に対する意欲を増す
・舌苔は味覚を鈍磨させると共に、カンジダ性肺炎の原因となる
舌は最も新陳代謝が激しい組織→放置すれぽ舌苔形成
●訪問歯科のまとめ
人間にとって食事は単に生命を維持するための栄養補給ではなく、会話は単なるコミュニケーションのメディアでほない。これは"ヒト"が"人"として存在する証しであり、文化である。
特に寝たきりの要介護者にとって食生活を維持改善し、言語機能を確保する口腔ケアは、社会的・文化的存在としての人間の姿を回復し、要介護者の自立とQOLの向上をめざす上で必要不可欠。
|