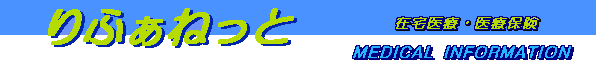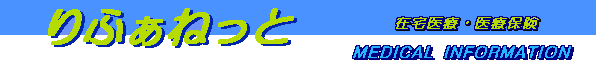| 3)食事介助の技法 |
| |
安全確保:吸引準備、緊急時の対応
食べる前に:嚥下体操、お口の清潔(口すすぎ・歯磨き) 姿勢、 |
| |
|
唾液(少量の水)嚥下(誤嚥は一日目に起こりやすい) |
| |
介助の一般的注意:介助者の視線の高さ、口にものが入っているときには話しかけない |
| |
|
一口量(ティースプーンー杯が適量)、姿勢と介助方法は対象者により選ぶ、体に対して頚をわずかに曲げた姿勢がよい
|
| |
|
障害の時期
|
食べさせるもの
|
食べさせ方
|
| 先行期 |
冷たいもの、味の濃いもの |
食事に意識を集中できる環境、ペース作り |
| 準備期 |
ある程度の粘りけとかたまり |
スプーンの使い方(舌の上におくように) 口唇閉鎖の介助 |
| 咽頭期 |
喉に残らない、ばらつかない |
嚥下を意識する、喉をもちあげる、声の聴取 咳払い、息こらえ嚥下 何回も飲み込む、交互嚥下(1、2ccの水)
うなづき嚥下、横向き嚥下、側臥位(健側下) |
|
| |
|
|
| 4)機能改善に関わる因子 |
| |
原疾患(進行性・非進行性)
回復への意欲、
日常活動性、
介護カ(マンパワー) |
| |
|