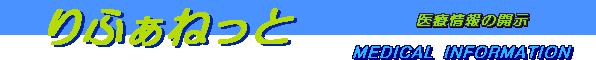 ● 自己の医療情報は自分でコントロールする ●2.再診時に ◇判るならば病名を聴く
診断が簡単にはつかない疾患もありますが、できるだけ「現段階では、どのような病気と考えられるのか」と病名を尋ねるようにしましょう。どの医者も懸命になって病囚の究明に頭を働かせてくれています。判断できない段階でもどのような可能性があるのか話してくれるでしょう。
◇検査デ―夕―を受け取る
できれば、血液検査や心電図の特別な不整脈のときなどには、コピーをもらったり、自分のノートにメモを取りましょう。医者の方でも検査結果を大切にされる方を尊重する気持ちがあります。
◇診療効果を医療者に伝える
初診からの治療の効果の様子をきちんと伝えましょう。効果が上がっているようですと、医療者もとても嬉しいものです。薬に関する副作用についても心配な点は話しましょう。 3.日常の診療の中で ◇医療記事や健康薬品についても相談を
自分の疾患と関連のある記事を切り抜いて来てくれる方には、頭が下がります。
◇がんの説明について
日本ではまだがんの「告知率」は高くなく、30%未満のようです。しかし、じりじりと上昇しています。
97年のがんによる死亡者の割合がついに30.1%となりました。(6月10日厚生省発表)がんは、いまではだれもがかかる可能性の高い疾患と認識され、さらに、21世紀には治癒率の低い肺・食道・肝・膵・胆といった、いわゆる難治がんの割合が高くなると予想されています。
◇「力ルテの開示」について
患者さんから希望があった場合には、医療者はカルテの内容を開示する義務があることを法定化しようとする動きがあります。両者の間の信頼関係をより強くするためには、とても良いことであり、当院ではこれまでも請求があった場合にはいつでもコピ一をして手渡すことを表明してきました。
「自分こそ主治医」の実現を考えていきましよう。
|
 

[ HOME ] |