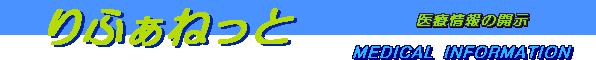 ● 住み慣れた家で死ぬということ ●神戸新聞で連載 No.4
開業医として往診など在宅医療に取り組んで行く中で、自然と亡くなっていく方をお見送りさせていただくようになった。最初はとりたてて在宅ターミナルケアを支える、といった理念があった訳ではなく、ただもう入院はしたくない、という患者さんを自宅で見ていたら、亡くなってしまった、というあっさりした感じだった。
末期癌のAさんの状態が悪くなり、呼んでも答えなくなった。きのうまでおかゆを少し食べていたのに。血圧も下がっている。でもAさんはいつものようにただ静かに座敷の布団に寝ている。点滴も、おしっこの管も、心電図のモニターも、何にもついていない。このまま本当になにもしなくていいのだろうか。医者としてただ見ているのが不安でしかたがなかった。
「畳の上で死なせたい。あれだけ入院はいやがっていたのだから。」奥さんの意志は硬い。やがて家族に見守られてAさんは草花が枯れていくようにだんだんと息をしなくなっていった。ああ、これが "息を引き取る" というやつだ。病院では感じたことのなかった死の自然な形を初めて教えていただいた。
しかし医者としての仕事がある。病院時代にはまず心電図のモニターで心臓が止まったのを確認していたせいか、患者さんの自宅で家族に囲まれながら死を確認することに戸惑いがあった。聴診器を落としたり、緊張しているのがわかる。それでも呼吸していない、もう亡くなっているんだ、と素人のように自分を納得させ、奥さんがうなずいてくれたのに勇気づけられてやっと「御臨終です」と告げることができた。病院時代には何百回と告げて来たこの言葉にこれほど責任を感じたことはなかった。
その後いろいろ失敗を繰り返し、家族に迷惑をかけたりしながら自宅で亡くなる方のお手伝をさせていただいた。そんな中で自宅で死ぬことが当たり前だけどすばらしいことのように思えてきた。住み慣れた家で家族やペットや家具や食器や見慣れた天井のしみに囲まれて人生最後のひとときをゆったりとわがままに過ごす。食事時間や消灯時間や面会時間の制限などいっさいの規則がなく自由な自分の時間と空間が自宅にはたっぷりある。そして患者さんのわがままを聞いて寄り添うようにふわっと支える医者と看護婦が必要な時にかけつければいい。死は病院の中、医療の中にあるのではなく、本当は死の一部に医療がちょこっとかかわるだけのはずだ。 誰もが必ず経験する死を日常の当たり前のものにしていく。住み慣れた家でのんびりと死んでゆく人を、家族や、近所のおばさんや、ヘルパーさんや、保健婦さんや、看護婦さんや、町医者がちょっとあわてたり、悲しんだり、あきらめたり、ほほえんだりりしながらなんとなくお見送りする。そんな"死の日常化"へ向けてゆったりとすすんで行きたい。
|
 

[ HOME ] |