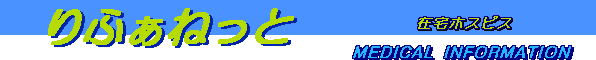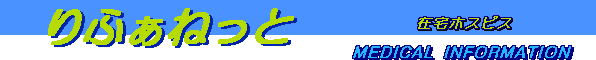
● パパらんの贈りもの ●
ある日の夕方、退社後いつものように病院によってから帰宅し、夕食を済ませた後、再び病院へ行った時のことです。夫は帰る私をいつもの様に1階まで送って降りてきました。そして夜来た時はいつもそうしていたように、誰もいなくなった待合室のソファーに腰掛けて話していました。夫は静かにではありましたが突然ポツンと
「僕の肝臓、本当は何なんや?」と、尋ねるのです。
すでにこのころから夫は肝臓への転移をうすうす気付いていたのかも知れません。私は医師が言われたようにやはり肝血腫だと説明するしかなかったのです。
その後、本当の事を伝えるという決心をするまでには随分悩み続けました。そして告げることを決めたのは、次の2つの事があったからなのです。それはまず子供たちの言葉でした。
「お父さんだって本当のこと知る権利がある。」
「がんを知らずに、退院したらまた無理をして治療を怠るかもしれない。」
「お酒が過ぎたりしたら余計命を縮めるかも知れない。」
と知らせることを強く願うのです。事実子供の言い分はその通りです。
◎ 私だってがんだったら教えてほしい。
◎ 夫は、本当に仕事熱心だった。
◎ 確かにお酒は好きで、時として過ぎることもあった。
それともう一つのこと、それは悩む私に助言を下さった婦長さんの言葉でした。
「長年信頼し合って築きあげて来られた生活です。私は告知の善し悪しは分かりません。
ただ、今のまま告知をなさらずにいてご主人が本当のことを知った時、またご自分の命に限りあることに気付かれたとき、裏切られたという思いをお持ちになられたとしたら、悲しいじゃないですか。」そっとこう話して下さいました。
この婦長さんは、ご自身の息子さんが病気のため3O才までの命と言われており、その息子さんに真実を告げておられます。そして息子さんは限られた命と知りながらも勉学の道を選び、今は大学病院で学ばれているというのです。そしてその婦長さんの言葉で私は夫に真実を伝えることにしました。やっと決心がついたのです
医師にもその旨伝えました。しかし私は、医師の口から知らせてもらうまでに、自分の口から夫に伝えたかったのです。医師との話し合いの結果、伝える日は昼から休暇を取り、病院にかけつけました。病室の夫のもとへ行くと、夫は抗がん剤の治療中でべットに寝ていました。医師との待ち合わせの時間は迫ります。私は夫の手を取り耳元に口を持っていき、小声で言いました。
「お父さん、ごめんね。本当は隠してたことがあったんよ。お父さんのがんね、本当は肝臓に転移しているんだって。」
その時夫は、何一つ動揺らしいものは見せずに、
「フ一ン、やっぱりそうやったんか。何となくわかっとったよ。」と言うのです。
伝えることを悩んだという私に「ご苦労さんだったね。」との言葉すらかけてくれるのです。でも余命についての話はしませんでした。そして主治医からの説明を夫は真剣に聞いておりました。主治医の元を辞した後も、夫の様子には何の動揺も感じられませんでした。或いは、精一杯の私たちへの思いやりが夫の心を占めていたのかもしれません。
退院までは穏やかに過ごしました。毎日、朝と夕方に夫を尋ねる息子と私をいつも笑顔で迎え、笑顔で送ってくれました。特に登下校の途中に自転車で見舞う息子を心待ちにしていたようです。普段そっけない態度で接する息子の優しさが嬉しかったのでしょう。
この春、姫路にも初めてホスピスが誕生していました。私は子供とともに見学に行きました。それは姫路市の北の外れにある姫路聖マリア病院の病棟に開設されたものでした。
改装されたばかりの病棟は美しく、病室も広く取ってありました。特に個室などかなり広々としていました。姫路市の中央近くを瀬戸内海に向かって北から南へゆっくりと流れる市川を東に見るべランダに出ると、初夏の緑や優しい川の流れが目にとまり、心休まる思いでした。私たちは、終末をここで迎えるかもしれない夫を思い、担当医師とも面談し、いろいろ話を伺いました。そして看護婦さんに案内され病棟内を見て回りました。ただ一つ不安だったといえぱ、ここは入院してしまえば今までのように子供たちが朝夕顔を出すのはかなり難しくなるのです。それでも息子などはよい環境で父親が過ごすことを望み、「僕自転車で来れるから、ここで過ごさせてあげようよ。」と言いました。
|