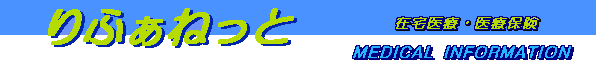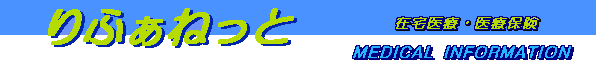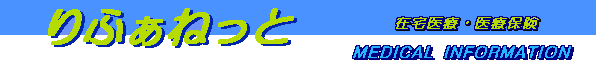
● 在宅高齢者ケアにおける摂食・嚥下障害
●
摂食 ・嚥下障害の機能訓練
〜「口から食べる」 意義をふまえて
提供: 大阪府作業療法士会学術局研修会
講演1 そのデイケア 小椋 脩
I.."食べる"こともコミュニケーシヨン
1.コミュニケーション
Verbal-communication :音声言語
Nonverbal-communication:表情・ジェスチャー・雰囲気(社会的文化的背景)宗教
食事(≠経口摂取)
2.食事の意義とその障害
1)生命維持
2)話しことばの基礎
pre-speechの概念,話しことばの前段階として食べる機能の発達
3)コミュニケーション
自己と他者との関係確認
家族との食事:既存の関係の再確認
会食・接待 :新しい関係を築く
食べ方(しつけ)による人物評価
4)情緒・心理・社会的発達
"おっぱい": 新生児にとっての初めてのコミュニケーション
家族団らん はずむ会話・食事マナーとしつけ→人間形成
食事を五感で楽しむように"関係"を楽しむ
健康でcommunicativeな"食事" 「何を食べるかより、いかに食べるか」
II.摂食・嚥下障害への対応
1)気道防御機能障害 2)栄養摂取障害 3)食の楽しみの喪失
嚥下障害:「ものを飲み込むことができない」
摂食・嚥下障害:「嚥下障害を含んだ食べることの障害」
1.摂食・嚥下障害へのアプロ―チ
1)評価・観察のポイント
経口摂取の危険度を把握し、関係者の共通認識とすること
摂食例(既に食べている)と非摂食例(NPO)で異なる危険性の把握
| 補助検査法の必要性の判断: |
窒息や(誤嚥性)肺炎の既往の有無、最近の発熱状況や喀痰の量や性状チェック、全身状態とバイタルサインなどによる患者・家族のニーズ、意識レべル、日常生活リズム、姿勢(特に頚部の運動性)
|
| 全体像(原疾患・病歴・問診・意識状態・高次脳機能・運動機能・感覚・反射など) |
代表的補助検査法
VFSS videofluoroscopic swallowing study
VESS videoendoscopic swallowing study
誤嚥の判定 むせとむせのない誤嚥silent aspiration
臨床的観察
*四肢の麻庫・失調、知覚障害(特に口腔顔面領域)
*姿勢バランス、頚部・体幹の運動性
*構音障害:準備期・口腔期に関わる器官の運動障害をある程度反映
*流涎の有無
*湿性榎声(wet hoarseness):声門上部の貯溜を示唆する兆候
*咳嗽カ:下気道防御としての喀出能力を計る、たいへん重要な機能
*空(唾液)嚥下、水飲みテストlcc,3cc,5ccなど
*呼吸コントロ―ル:吸気→嚥下時無呼吸→呼気
*摂食場面観察:食物形態、摂食ペース(介助 自カ摂取)、食べこほし
食事への注意集中(環境的要因) むせの回数と程度
2)アプロ―チ
間接(基礎)訓練:基本的に食物を用いない;安全性が高い
直接(直接)訓練:段階的摂食訓練に代表される食物を用いる訓練:食物形態・体位
代償的方法、誤嚥の危険を伴うが実際的な訓練
|