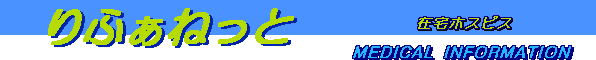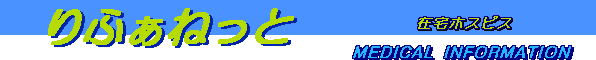
● パパらんの贈りもの ●
その頃、D医師が夫を見舞って下さいました。病室に入って来られるなり夫の顔を見て、
「おお、元気そうじゃないですか。顔色もよろしいな一。」
と、不安も吹っ飛んでしまいそうな激励の言葉をかけてくださいました。夫の笑顔は、一層輝いた様に見えました。いつも思っていたことですが、この方は常に対話する相手の話を肯定的に受け止めて話を進めていかれるのです。まるで人の心に眠っている自信を揺り起こして下さるかのような話の進め方をなさるのです。廊下まで送って出た私に、まだもう少しの間は元気でいられると思っていたこと。悪化の早さに驚かされたことなど話され、私にねぎらいの言葉を下さって帰って行かれました。
この頃になると、夫はしきりに家に帰りたがるようになりました。それは、
「なー。おうちに帰ろうよ−。」という言葉で始まりました。
この言葉を聞いた私は、何とか夫の望むようにしたいと考えました。しかし、現実にはそれは無理なことでした。主治医は今は動かせる状態ではないと言われました。それは同時にもう動かせる状態には戻らないという宣告なのです。娘もそっと首を横に振ります。父親が大好きでずっと父親の側で看病をしてくれている娘です。私なんかよりもっともっと連れて帰りたかったはずです。冷静に見つめていた娘だからこそもう既に動かすことは出来ないと判断したのでしょう。
病院での終末を覚悟していた夫も、やはり心の底では家での治療を望んでいたのでしょう。しきりに家に帰ろうということを繰り返す様になりました。その度に私は辛い思いで、
「お父さん、今状態がちょっとよくないの。もう少し回復してからにしよう。」と夫にうそをつきました。
そう言いながらも心の底では「ごめんなさい」を繰り返していました。
やがて、夫は一日のうち眠っている時間が長くなりだしました。窓のカ−テン越しの夏の日差しが柔らかく病室を包んでいました。静かに眠る夫を娘と私はじっと見っめていました。そんな時間が私にはとても平和な時の様に思えたのです。娘がふと、
「平和やね一。」と言いました。
私も静かに「うん、ほんまに平和ねー。」と答えました。おそらく二人ともどうぞこの時間が長く続いてほしいと思ったからに違いありません。夫がいなくなってしまうなどと思いたくなかったのです。
|