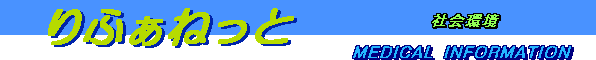 ●「遥けくも遠く」●
園内には五日ごとに奉仕日というはがあった。午後1時分館前の広場に集められ、宮城遥拝して、分館長の訓示があった。五日間の療養生活中に園則に沿わない行状の者に説教するのだ。もっとも良くない者は一歩前進、多くの人の前にて悪行を暴かれるそれが終わると、肥桶一つを渡され、二人一組で棒をさし職員経営の農場まで運ばされる。経験のない二人は足が揃わず、満杯の肥桶はかっぽん、かっぽんと跳ねる。それがときには着物に飛び散るからかなわない。こうして病室から農場まで五回往復の割り当てであった。困ったのは着物の代わりを持っていない。
私の最も嫌な仕事、それに怖さと言えばこれ以上なかった。僚友が亡くなれば火葬するが、その仕事は入園者と決まっていた。お前の当番になっているから今夜は行くんだ、と寮長の命令、あの頃なぜ夜になって火葬がなされたのだろう。先輩達は何の苦もなく、鼻唄を歌いながら火葬していた。焼けたことを確認し帰る。翌朝早々に出かけ、かまのふたを開けて遺骨拾いを待つのが役目であった。
いろいろな作業があり包帯再製の洗濯は入園者の仕事で、どんな仕事でも無報酬である。こうして新生園は運営されていたが、戦争は激しくなるばかりで若い男子職員は軍隊に召集されて行った。その補充の職員の就職はなく、入園者の負担になっていった。寮の前など、適当な場所を探して防空壕を掘り汽缶場(ボイラー室)の石炭がなくなると、近くの駅に行き、スコップで車に積む仕事、米がなくなると食糧営団までいき米俵を担ぐ。人出が不足すると炊事場に、汽缶場にと働く。燃料が入らなくなり園外の山林の木を買い伐採して元気な者みんなで背負って運ぶ、経験者が居たことを幸いに炭窯を作り木炭をつくる。病友の看護、不自由な僚友の介護、その他多くの作業があり、若い僚友が多かったので運営することが出来た。
こうして終戦を迎え、ホッとしたものの何につけても無いものぱかり、園内の空地は畑に開拓され食事を補うことが出来たが、みんな手足を痛めてしまった。生活の場としての所であり、国立療養所としての存在は薄くなり、生きようとする気持ちが強く、自治会の設立を見ることになった。このような歩みの中に予防法なるものを知らなかった。知ることが出来たら、園外に出てまで園の為に働くことは許されないはずであった。園を運営するには法律を矛盾に扱ってまでなされた訳である。それで予防法の改正を望んで運動し続けたのであった。私達の願いがかなえられ、平成八年四月一日をもって法律は廃止され、新聞やテレビで報道された。これを知って喜んでくれたのは、私達と関係ある人々だけである。 私の両親はこの世を去って久しい。私は一番先に伝えたいのは親にであった。それで冒頭の短歌が出来たのである。自分の子として親はどんなに悲しんだか知れない。妹達は電話でよかったと喜んでいたようだが、家に帰って来いと言わなかった。それ は警官が護衛してまで収容しなければならない悪病、それはその法律が廃止されても、私の収容される時の状況を部落の人も親類の人々も知っている。それが家族に偏見として残っている。私には強い劣等感としてこびりつき、社会の中に潜け込むことは 出来ない。こうした汚点を残しているのは政府の責任である。 (1997年8月)
|
 
本文は朝日新聞大阪厚生文化事業団編集による「遥けくも遠く」 [ HOME ] |